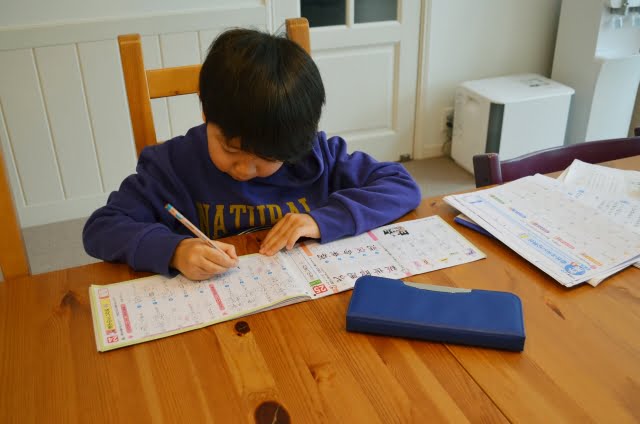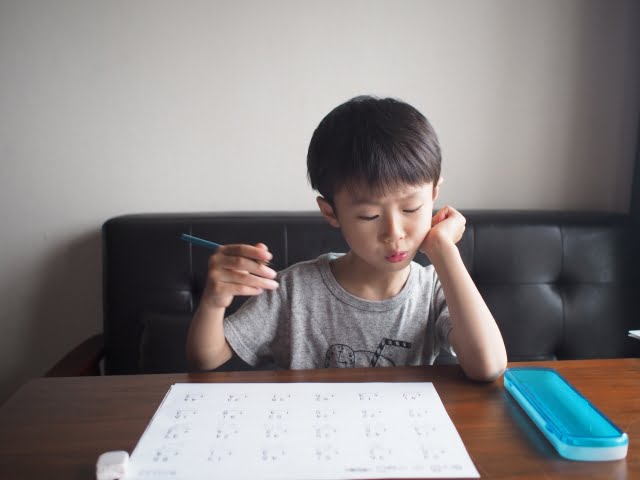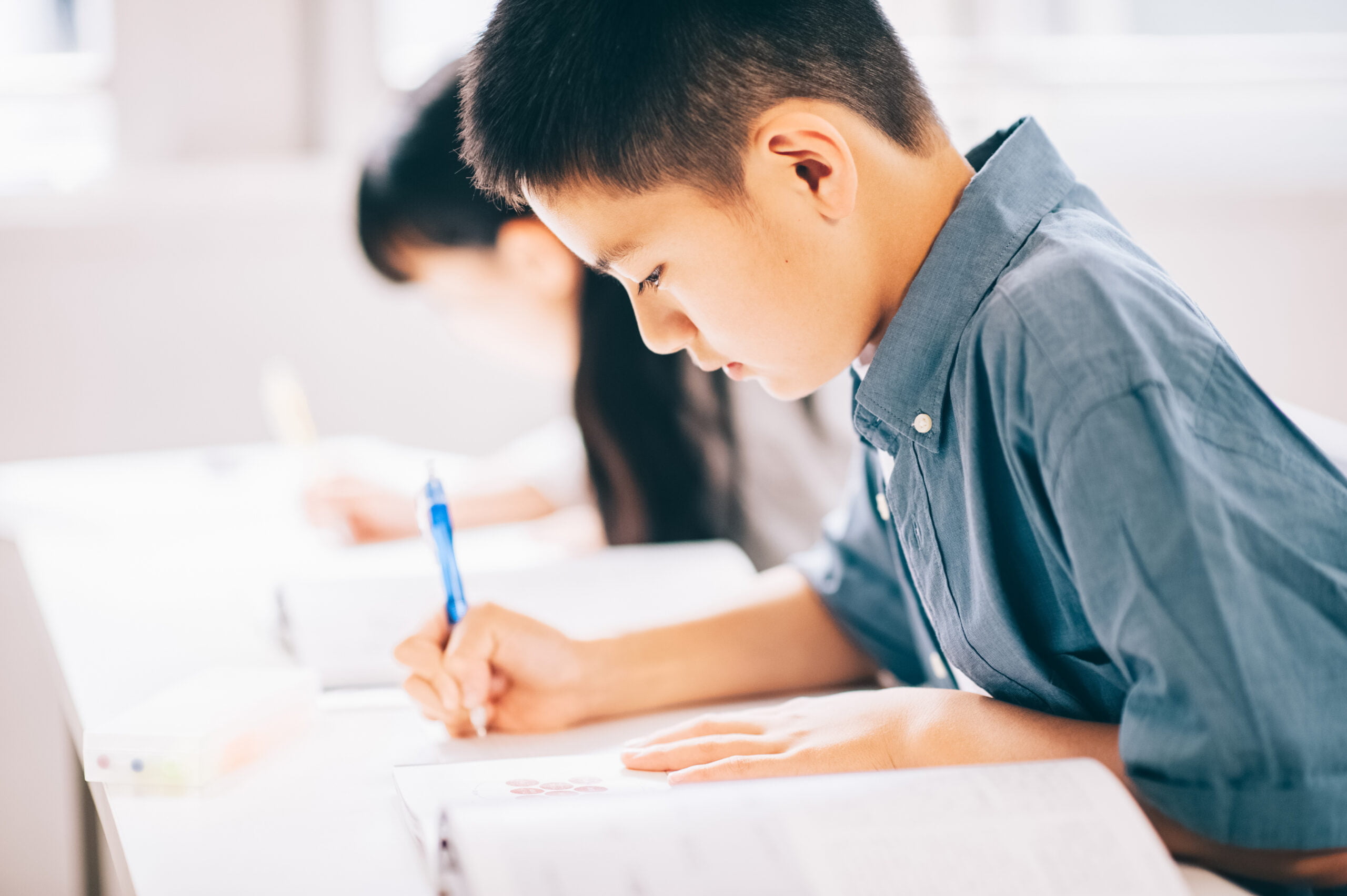【時短勤務は何歳まで?】3歳・小1・小4で時短終了!フルタイム復帰後のリアルな経験談
\ 【登録無料】1分で完了/
※会員登録ページへ移動します
時短勤務は、仕事と育児・介護の両立を支援する制度ですが、期間には制限があり、子供が3歳までとしている企業が大半です。期限後はフルタイムに戻す必要があり、働き方に悩む人もいます。この記事では、時短勤務の概要や期間、そして期限後の働き方について解説します。将来的なキャリアをイメージするのにお役立てください。
時短勤務とは?

時短勤務とは、通常の所定労働時間よりも短い時間で働く勤務形態のことです。
育児・介護・健康上の理由などによりフルタイムでの勤務が難しい人が利用できる制度であり、雇用形態は正社員のまま、働く時間だけ短縮できます。
なお、時短勤務は育児・介護休業法第23条・第24条で定められた制度(※)であり、導入が義務付けられています。
対象となる従業員からの申し出があった場合、企業規模・業種問わず時短勤務を取得できるので、誰でも利用可能です。
(※)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov 法令検索
時短勤務の対象者
時短勤務の対象者は、以下の通りです。
- 3歳未満の子供を養育している、または要介護状態の家族がいること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者(1日限りの雇用契約または30日未満の有期契約で雇われている労働者)でないこと
- 労使協定により定められた適用除外者ではないこと
「その他会社が認めた従業員」には、治療・通院など健康上の理由がある人、障害のある人、高齢者などが含まれます。
会社の許可があれば、学業やワークライフバランスとの両立を目的に時短勤務を取得することも可能ですが、あくまでも企業が独自に制度設計している場合に限定されます。
反対に、育児・介護休業法第23条・第24条で定められている「育児中の人」「介護中の人」であれば比較的容易に時短勤務の取得が可能です。とはいえ、育児中であっても「入社1年未満の人」「週の所定労働日数が2日以下のパート社員」などは、会社によって対象外となることがあるので注意しましょう。
時短勤務の労働時間
「時短勤務の労働時間は〇時間にしなければならない」という、法的な定めはありません。
原則として1日6時間勤務(例:9:00〜16:00 ※休憩1時間を含む)が基準ですが、実際には「最低6時間」の範囲で時短勤務ができる企業が多いです。
つまり、「1日7時間労働」「1日8時間労働」など労働時間を選択できるので、「時短勤務でもなるべく長く働きたい」などの希望を出すことも可能です。
また、会社が認めている場合、「1日5時間」など6時間を下回る労働時間にすることもできます。
どの程度柔軟な制度設計になっているかは会社により異なるため、確認しましょう。
時短勤務中の給与はいくら?
時短勤務中の給与は、労働時間に比例して算出されます。
例えば、フルタイムと比較して労働時間を3分の2に短縮した場合、給与も3分の2で計算されます。
ただし、賞与(ボーナス)や各種手当の扱いは企業ごとに異なるので、「想像以上に給与が減った」というケースも少なくありません。
反対に、「フルタイムでも時短勤務でも一律の賞与(ボーナス)を受け取れる」という企業もあり、制度設計には大きな差があるのが現実です。
これから時短勤務を取得する方は、事前に自社の制度をチェックしておきましょう。
時短勤務は何歳まで取れる?

時短勤務できる期間は、育児理由の場合「子供が3歳の誕生日を迎える前日まで(※1)」、介護理由の場合「対象家族1人につき通算93日まで(分割可能)(※2)」と規定されています。
つまり、育児理由で時短勤務を取得する場合、子供が3歳を迎えて以降はフルタイムに戻す必要があります。
子供が3歳の誕生日を迎えた時点で、企業に「時短勤務制度を継続する法的義務」はなくなります。
保育園や幼稚園の預かり延長時間を確認したり、配偶者や祖父母との協力体制づくりが欠かせません。
(※1)そのときのために、知っておこう。育児休業制度|厚生労働省
(※2)そのときのために、知っておこう。介護休業制度|厚生労働省
時短勤務の延長
会社によっては、時短勤務の期間を延長できるよう、独自に制度設計している場合があります。
育児理由で時短勤務を取得している場合、「子供が小学生になるまで」「子供が小4になるまで」と期限を延長できることがあります。
また、時短勤務できる期間に期限がなかったり、家庭都合に合わせて取得できたりする企業もあるのでチェックしてみましょう。
ただし、時短勤務の延長はあくまでも企業独自の制度であり、法律で定められた施策ではありません。
厚生労働省の育児・介護休業制度に関する事業所調査によると、最も割合が高いのは「子供が3歳になるまで」としている会社(38%)です。
「小学校入学~3年生まで」時短勤務を延長できる企業の割合は6.6%しかなく、大半の場合は小学生になる前に時短勤務できる期限がきてしまうとわかります。
つまり、原則として時短勤務を延長することはできず、子供が3歳を迎える段階でフルタイム勤務に戻す必要があるということです。時短勤務の延長制度はあくまでも企業の判断に委ねられていて、法律上必須でない点に注意しましょう。
参考:「事業所調査 育児・介護休業制度等に関する事項」|厚生労働省
3歳までしか時短勤務できないとき大変だったこと

子どもが3歳になるまでしか時短勤務できない場合、3歳になってすぐフルタイムに戻す必要があります。その場合に生じる問題点を下記にまとめていますので、チェックしてみましょう。
保育園のお迎えに間に合わなくなる
通勤時間次第では、保育園のお迎えに間に合わなくなる可能性があります。
多くの保育園では閉園を18時もしくは19時と定めており、保護者はどんなに遅くとも閉園までに子どもを迎えに行く必要があります。もし定時が9時から18時までであれば、残業なしですぐお迎えに向かったとしても閉園ギリギリになることが多いでしょう。
業務の進み具合や交通網の遅れ次第では時間に間に合わず、保育園に多大な迷惑をかけてしまう可能性が考えられます。なかには定時が10時19時という会社もあり、フルタイムでは物理的に働けないということも考えられます。
今の会社でフルタイム就労した場合、余裕をもってお迎えに行けるかシミュレーションしておくことが大切です。
寝かしつけが遅くなり子どもの睡眠時間が減る
フルタイムにしてお迎えの時間が遅くなると、その分夕食や入浴の時間も後ろ倒しになり、子どもの睡眠時間が削られます。
朝も早めに出勤する可能性があることを考えると、送りを早めに済ますため起床時間が前倒しになることも含めて検討しておく必要があります。
上記のグラフは、年齢別の平均睡眠時間を表しています。未就学児のうちは10~11時間の睡眠を確保している家庭が多く、それ以下になると睡眠不足が不安視されます。
最低限必要な睡眠時間を確保できるかも、十分検討しておく必要がありそうです。
子供と遊べる時間が減る
3歳前後の子はまだ親の手がかかる時期。保育園で頑張っているぶん「帰ったらお父さんお母さんと遊びたい」「親に甘えたい」と思うのは自然なことです。
しかし、フルタイム勤務が原因で時間がない場合、「ママ見て!」「一緒に遊ぼう!」という子供の声に答える余裕がなくなるかもしれません。
忙しさに追われ子供と過ごす時間が減ることに、「親と過ごす時間より保育園の先生と過ごす時間の方が長い…」と罪悪感を覚えるママは多いです。
子供本人がストレスフリーに楽しく毎日を過ごしていれば問題ありませんが、いつもと違う様子が続くときや、子供との時間をじっくり取りたいときは、働き方を見直してみるとよいかもしれません。
家事に手が回らなくなる
未就学児のうちは、着替えの枚数に合わせて洗濯を増やしたりおねしょの処理をしたり、家事が多くなりがちです。
遅い時間に帰宅して子どもを急いで寝かしつけたとしても、親自身が疲れきっていてなかなか家事に手が回らなくなることもあるでしょう。
もちろん時短家電や家事代行を使って賢く家事をやりくりすることもできますが、「自分で家事ができないこと」自体をストレスに感じてしまう人は多いものです。
家事と育児と仕事との間で板挟みにならないよう対策する必要があること、時には家事を放置することも出てくることを覚悟しておきましょう。
小1までしか時短勤務できないときに大変だったこと

幸いにも3歳を超えて時短勤務できる場合でも、小1のタイミングまでとされているケースも多いです。
小1はちょうど小学校入学のタイミングに被るので、思わぬ落とし穴があるかもしれません。ここでは、小1になるまでしか時短勤務できない場合の問題点を紹介します。
いわゆる「小1の壁」については、下記の記事でも解説しているので参考にしてみましょう。
宿題や翌日の授業準備に手が回らなくなる
小学生になると毎日宿題が出されますが、入学してすぐ全て自分で解決できる子は少ないです。始めのうちは親が連絡帳をチェックし、今日の宿題を確認して一緒に進めていく必要があると思っておきましょう。
ある程度ひとりでできるようになってからも親の丸付けや音読チェックを求める宿題は意外と多く、完全に手が離せるようになるのはまだまだ先のことです。
また、翌日の時間割をチェックして教科書やノートを揃えたり、鉛筆・消しゴムなどの文房具に欠けがないかチェックしたりすることも大切です。
フルタイムで働く場合なかなか勉強面をサポートする時間が取れず、子どもにもどかしさを感じさせてしまうこともあるので十分な配慮が欠かせません。
夏休み中も含めて毎日学童を利用する必要がある
小学生になると保育園がなくなるので、夏休み中も含めて毎日学童を利用する必要があります。
子ども本人が学童を楽しんでくれていれば問題ないものの、なかには「仲のいい子はみんな学童に行っていないのになんで自分だけ?」「せっかくの夏休みなんだから親や友達と遊びに行きたい」と感じる子もいるでしょう。
保育園以上に多様化する集団生活のなかで自分の家庭環境に気づき、フラストレーションを抱える子も多いのです。また、毎日お弁当を作る親側の負担も大きく、送迎や閉所時間に気をつけて働くストレスはこれまで通りのしかかります。
習い事を入れて適度にリフレッシュさせたり、親の力を借りてお出かけの機会を作ったりすることもできますが、毎日可能とは限りません。
子どもの精神面もしっかりケアできるよう、方法を見つけておく必要がありそうです。
学童の閉所時間次第では小1から鍵っ子生活が始まる
学童の閉所時間は、地域や利用先の学童によりさまざまです。
保育園と同じく19時頃まで預かってくれる民間学童もあれば、学校併設の学童であれば17時頃閉まってしまうこともあるので注意が必要です。
閉所時間次第では、学童が終わってからひとりで自宅に帰る鍵っ子生活になる可能性があります。
学童後に集団下校を利用できるか、小1から鍵っ子生活ができるか、万が一の怪我・事故・火事などが起きたとき近隣に頼れる人がいるかなどシミュレーションをしておきましょう。
なかには「小1から鍵っ子生活は不安が大きい」として、フルタイム就労を諦める保護者もいます。
子供の甘えを受け止められる時間が少なくなる
小1になると、少しずつ着替えなどの身支度や物の管理が自分でできるようになり、つい求めることが大きくなってしまいがち。
しかし、小学校低学年の時期は、まだまだ親への甘えが必要な時期でもあります。
一気に広がる友達関係や、毎日きっちりとした時間割通りに進む集団生活で、ストレスを抱えてしまう子は少なくありません。
本当であれば放課後にゆっくり自宅で過ごしたり、親に話を聞いてもらったりするのが理想的ですが、時間的な余裕がないと後回しになってしまうことも。
料理・洗濯・掃除などの家事や、宿題チェック・習い事管理に追われているうちに、「もう1年生なんだから」「自分のことは自分でしなさい」というスタンスで接してしまうことが増えるかもしれません。
一気に労働時間を増やした結果、後から「もう少し甘えを受け止めてあげればよかった」と後悔しないよう、慎重に判断していきましょう。
小4までしか時短勤務できないときに大変だったこと

小4になると宿題や翌日の授業準備など最低限のことはひとりでできる子が増えるので、時短勤務からフルタイムに切り替えても問題ないと感じる人が多いでしょう。
自分でお風呂に入ったり寝たりできる子も多く、「子どもの世話をする」という意味では各段に楽になっていきます。
しかし、小4には小4の悩みがつきものです。下記で小4になるまでしか時短勤務できない場合の問題点に触れていきます。
いわゆる「小4の壁」については、下記の記事でも解説しているので参考にしてみましょう。
本格化する中学受験対策をサポートできない
小4は、中学受験対策が本格化する時期でもあります。
有名かつ偏差値の高い一貫校を希望する家庭や都心であれば小3から受験勉強に入るケースも多く、「中学受験を希望するなら遅くとも小4からの対策が必須」と考えるのが一般的です。
塾のコマ数や夏期講習などの季節講習が増える学年でもあり、3~4年間の長期的なマラソンが始まることを親子ともに覚悟しなくてはいけません。
とはいえまだ遊びたい盛りの小学生が、数年後の将来を見据えて勉強一本で努力していくのは至難の業です。
親が学校や塾と上手に連携し、宿題・モチベーション・メンタルを細かくサポートしながら伴走し続ける必要があるので、相当の時間が割かれます。
時短勤務できずフルタイムになると勉強の進捗がわからなくなり、本人任せの受験になって失敗してしまうこともあるので注意が必要です。
学童を卒業しなくてはいけない地域がある
2015年に制度が変わったことで小学校卒業まで学童を利用できるようになったものの、受け入れ態勢が整っていない学童は未だに多いのが現状です。
低学年の児童を優先するため受け入れ対象を小3までとしている学童は多く、それ以降の児童は放課後クラブや地域のボランティアに任せられることもあります。
その場合、閉所時間が早まるなどこれまで通りの預け先として利用できなくなる可能性もあるのです。
学童を卒業しなければいけない地域では、その後の預け先をどう確保するか早めに検討しておくことが大切です。
民間学童など人気の高い預け先は、相当早い段階でいっぱいになってしまうこともあるので要注意です。
反抗期が始まる子どもの精神的なサポートができない
小4頃から反抗期が始まる子が多く、親の言うことに素直に耳を傾けなくなることが想定されます。
学校で問題行動を起こして呼び出されたり、友達同士のトラブルに巻き込まれて保護者同士の調整が必要になったりすることもあるでしょう。
このタイミングで時短勤務からフルタイムに変わってしまうと子どもの精神面をサポートしづらくなり、より親子間の溝が深まりかねません。
反抗期は個人差が多く、予測が難しいものです。
どんなに忙しくても、いざというときはすぐに子どもの声に耳を貸せる体制を作ることが大切です。
習い事の時間を確保できない
小4になると習い事をする子が増え、「自分も習い事をしたい!」と言われる可能性があります。なかには送り迎えが必須な習い事もあるので、フルタイムでも無理なく習い事に送り出せるか検討しておきましょう。
すでに習い事を始めている場合、フルタイムに切り替えてもコースや曜日を変更しなくてよいか考える必要があります。
場合によっては同じコースの友達と離れてしまうこともあるので、子どもの理解を得られるか、慎重に判断していくことが欠かせません。
増えていく友達との関わり方に関与できない
小4頃になると、友達同士で約束して放課後に遊ぶことが増えるなど友達付き合いが加速します。
社会性を広げる貴重なきっかけになる一方、些細な出来事でいじめや家庭間トラブルになってしまうこともあるので目が離せません。
なかには、親が帰宅するまで鍵っ子家庭に多くの同級生が出入りするなど、地域の目が届かない場所でトラブルになってしまうこともあるようです。
時短勤務ができなくなってからの働き方は?

時短勤務できる期限が切れてしまうときは、以下いずれかの選択をすることになります。
代表的な働き方を紹介するので、自分の家庭のライフサイクルや生活習慣をあてはめながらシミュレーションしてみましょう。
家族で協力しながらフルタイムで働く
時短勤務ができなくなった場合、多くの方はフルタイムで働くしかありません。
働く時間が長くなるので、保育園・学校・習い事の送迎や、平日の夜の自由な時間に影響が出るでしょう。
でも、家族で協力してやりくりできるなら、フルタイム勤務でも問題なく働けます。
フルタイムで働くことには、「時短よりも収入が増える」「キャリアアップのチャンスが広がる」など良い面もあります。
子供が大きくなってきたタイミングでフルタイムに戻すママも多く、フルタイムが一概に「両立できない働き方」になるわけではありません。
ただし、「通勤に時間がかかる」「子供が長時間親と離れるのを嫌がる」「ママ自身が疲れや不安を感じている」という場合は、無理をしないことが大切です。
急に限界がきて仕事を辞めてしまうと、保育園や学童が使えなくなったり、再就職が難しくなったりすることもあるので注意しましょう。
会社に相談して時短勤務を続けさせてもらう
会社に相談して、時短勤務を続けさせてもらう方法もあります。
育児介護休業法で定められているのは「最低でも子が3歳になるまでは時短勤務を認めること」であり、3歳以降も時短勤務を継続することへの制限はありません。
つまり、会社の承認が取れれば、3歳を過ぎても時短勤務を続けられる可能性があるということです。
実際に、「子供が小1になるまで」「子供が小学校を卒業するまで」と期限を長めに設けて時短勤務の制度を運用している企業もあります。
ただし、会社の就業規則で「時短勤務は子が◯歳になるまで」と明確に決められている場合、自分1人のためのルールを変えるのは難しいでしょう。
「できる限り配慮したいけれど、社内ルールを大きく外れるわけにはいかない…」というのが、会社側の本音でもあります。ダメ元でもいいから相談してみる、という気持ちで臨むのがよいでしょう。
テレワークやフレックスを使って柔軟に働く
フルタイムで働くことになっても、テレワークやフレックス制度を使えば、仕事と生活のバランスを保ちやすくなります。
例えば、テレワークなら通勤時間がかからない分、ゆとりができます。
自宅で働ければ保育園や小学校が近くなるので、途中で外出してイベントに参加したり、子供が急に具合が悪くなったときにすぐ迎えに行けたりするのもメリットです。
フレックス制度がある場合は、家族と相談して送迎の時間を調整するなど、柔軟に働く工夫ができます。
子供の予定に合わせて働けるのが魅力で、朝の通院や夕方の習い事に対応できるかもしれません。
2025年10月からは「柔軟な働き方を実現するための措置等(※)」として、月10日以上のテレワークが推奨されます。
時短勤務・始業時刻の調整などと組み合わせての利用も推奨されており、今以上にテレワークしやすくなることが期待されています。
ただし、テレワークやフレックス制度が使えるかどうかは会社によって異なります。
自由にテレワークやフレックスが使える会社もあれば、出社が必須の仕事もあるので注意しましょう。
まずは、自分の会社にその制度があるかどうか、どの程度の頻度で利用できるかを確認してみましょう。
期限のない「時短正社員」として転職する
時短勤務に期限がない会社を選び、「時短正社員」として転職する方法もあります。
子が3歳を超えても時短で働きたい人や、小学校に入ってからも子育てに時間をかけたい人におすすめです。
長期間時短勤務ができれば、子育てに必要な時間をしっかり取れるだけでなく、自分の時間も確保しやすくなります。
子供の年齢に関係なく長く働き続けることができ、途中でキャリアが途絶えることもありません。
ただし、最初から時短勤務ができて、かつ時短勤務できる期限を設けていない会社はまだ少ないのが現状です。
普通の転職サイトでは条件に合う求人が見つかりにくく、「やっぱり無理かも…」とあきらめてしまう人も少なくありません。
そこでおすすめなのが、リアルミーキャリアの「時短正社員に特化した転職エージェント」です。
専門のエージェントなら時短勤務が可能な求人が多く、自分のスキルややりたい仕事に合った会社を紹介してもらえるので、効率よく転職先を探せます。
【体験談】時短勤務できる期限が切れたけど…
リアルミーキャリアには、時短勤務できる期限が切れてしまい、転職や働き方の変更を決断した人の体験談が集まっています。
- 3歳で時短勤務が切れるが、フルタイムに戻すことは考えられなかった
- フルタイムに戻すと保育園のお迎えに間に合わず、転職を決意した
- 時短正社員として転職した結果、小1の壁や小4の壁にも対処できた
- 時短もフルタイムもどちらも可能な会社に転職して安心できた
時短勤務できる期限に関するお悩み・対処法は、以下でも紹介しています。
時短勤務できる期限に制限がある企業はまだまだ多く、かといって全ての企業でリモートワークやフレックスタイム制度を使ったフレキシブルな働き方ができるとは限りません。
3歳・小1・小4など子供の成長の節目を迎える目に働き方を見直し、どうしても無理が生じそうなときは思い切って転職を決断するのもひとつの手段です。
まとめ|時短勤務を続けたいならリアルミーキャリアへ
時短勤務できるのは基本的に子が3歳になるまでであり、それ以降時短勤務できる会社であっても小1または小4になるタイミングで期限がきてしまうことがほとんどなので注意しましょう。
子の年齢に関わらず時短勤務したいときは、時短正社員として転職するのがおすすめです。
リアルミーキャリアはワーママ向け時短正社員特化型の転職エージェントであり、入社直後から時短勤務できる求人や期限のない時短勤務求人を多数扱っています。
将来の働き方に不安のある人、今まさに時短勤務が近づいていて困っている人は、お気軽にご相談ください。
ワーママ特化型の転職エージェント「リアルミーキャリア」の特徴

【リアルミーキャリアの特徴】
①育児との両立が整いやすい求人紹介
┗時短・リモート・フレックスなど
②手軽に転職活動できる
┗やり取りはすべてLINEでOK
③キャリアアドバイザーはワーママ多数
┗共感力&提案力バツグン
④入社までのサポートをおまかせ!
┗書類作成代行・面接対策などもOK
リアルミーキャリアは、ワーママに特化した転職エージェントです。
取り扱っている求人は、制限なしの時短勤務やリモート、フレックスなど、柔軟に仕事ができる環境がそろっています。
※会員登録ページへ移動します
ママ友に教えたい率95%!リアルミーキャリアで転職した方の声
転職活動を終了された方へアンケートを取った結果、「リアルミーキャリアを他の人に勧めたい」と回答した方は95%※でした。
サービスをご利用いただいた方の声を一部ご紹介します。

リモートワークができるようになり、前より子供との時間が持てるようになりました。中抜けで通院できることも転職して良かったなと感じています。
これまでずっと立ち仕事だったので、デスクワークでの肩凝りは初体験です。でも小さなことですが、自由にトイレにいけたり、飲みたい時にコーヒーが飲めることも仕事によってこんなに違うんだなぁと感じています。
(30代 インサイドセールスへ転職)

毎日バタバタで大変ですけど、勤務時間が「私の時間」になり、とっても充実していて、イキイキしています。
同期、先輩方、上司共に皆さん本当に良い方で、何よりママが多い事が心強いです!!!
改めて素敵な企業を紹介して下さった事に感謝申し上げます。
社内にリアルミーから入社した人が多く、みんな口をそろえて「リアルミーめっちゃ良い」と言っています。
(30代 経理へ転職)
※アンケート実施時期:2020~2024年、有効回答数:762
時短正社員で転職するなら、「リアルミーキャリア」。
キャリアアドバイザーは8割がワーママなので、あなたの状況やご希望に寄り添った転職支援が叶います。
※会員登録ページへ移動します