育休中にボーナスはもらえる?税金や社会保険料はどうなる?
\ 【登録無料】1分で完了/
※会員登録ページへ移動します
育休中は育児休業給付金の支給を受けられますが、働いていたときの同額にはならず、どうしても家計が苦しくなってしまいがち。
そんなとき、年2回程度支給されるボーナスがあれば大きな助けとなります。
ただし、育休中にボーナスが支給されるかは会社により異なるので注意しましょう。
もともと育休中の人にはボーナスがない就業規則になっている可能性があり、事前に社内のルールを把握していないと「ボーナスがもらえないのは想定外だった」ということに陥ります。
また、業績の悪化や制度変更により全体的にボーナスがカットされている場合、会社の今後が気になってしまうこともあるでしょう。
成長可能性が低く、将来性が期待できないのであれば長い目を見て早めに転職しておく必要があるかもしれません。
本記事では育休中のボーナスについて解説しながら、ボーナスに対して発生する税金や社会保険料も同時にお伝えしていきます。
業績の悪化が不安なら育休を期に転職することも可能

ボーナスは、会社の業績に応じて支給されるものです。
業績が良ければボーナスも高くなりますが、反対に業績が悪化しているとボーナスの減額・不支給が起こります。これは育休取得有無に関係なく、全ての従業員に言えることなので注意しましょう。
育休中に会社の業績が悪化している場合や、今後の将来性が不安な場合は、思い切って育休を期に転職するのもひとつの手段です。社内外からの評判が高く、成長可能性もある会社に転職できれば、安定したボーナス支給が期待できます。
ワーママであれば時短勤務での転職になる場合もあるため、ワーママ・時短社員専門の転職エージェントに相談しましょう。
育休中にボーナスがもらえるかは会社により異なる
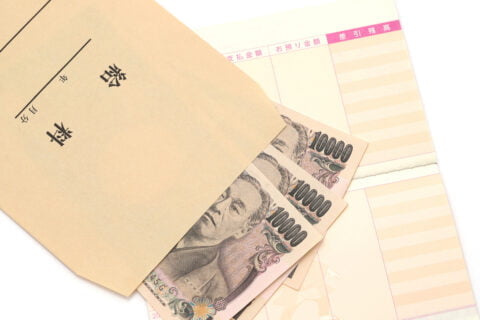
結論からお伝えすると、育休中にボーナスがもらえるかは会社により異なります。
以下では、「満額支給されるパターン」「減額支給されるパターン」「一切支給されないパターン」とに分け、それぞれの詳細を解説します。
満額支給されるパターン
就業規則・賃金規定等に休職中のボーナスについて明記されていない場合、原則として休職中でもボーナスを満額もらうことが可能です。
男女雇用機会均等法第9条第3項では「妊娠・出産など厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取り扱い」を禁止すると明記されています。(※)
具体的な不利益取り扱いの例として「減給または賞与等において不利益な算定を行うこと」と記載されているため、妊娠・出産・育児だけを理由にボーナスを支払わないという処遇は認められません。
休職中でも、ボーナスを受け取る権利は十分にあると考えてよいでしょう。
とはいえ、ボーナスは固定給のように雇用契約書で定額の支払いが約束されたものではなく、支給額・支給のタイミングは会社側の裁量に委ねられています。
事前に就業規則・賃金規定をチェックしたり、産休・育休を取った人の事例について調べたりしてみるとよいでしょう。
(※)厚生労働省「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止について」
減額支給されるパターン
休職するタイミングや期間によっては、ボーナスが減額支給されるケースもあるので注意しましょう。
特に就業規則や賃金規定により休職とボーナスの取り扱いについて明記されていた場合、記載されているルールに従って算定されることとなります。
例えば「賞与算定期間中に休職した日が含まれる場合、出勤日数により日割りで計算した額を支給する」と明記されていることがあるので注意が必要です。
育休は「欠勤」の扱いにならないものの、「出勤」もしていないため算定基礎が削られてしまうことがあるのです。
なお、育休中ボーナスに関する実際の判例も出ているのでチェックしてみましょう。
欠勤日数に応じて賞与支給額を減額すること、および育休期間中も同様の扱いをすることは問題ないとする判定が出ているため、減額したからといって直ちに法令違反となることはありません。(※)
産休・育休取得者だけに賞与を支給しないのは「育児を事由とした不利益取り扱い」になるため違法、産休・育休・介護休暇・私傷病休暇含め全ての休職に対して一律の賞与算定方式を適用するのであれば違法でない、と覚えておくとよいでしょう。
(※)裁判所 労働事件裁判例集「平成13(受)1066 東朋学園賞与請求」
一切支給されないパターン
就業規則や賃金規定に「賞与算定期間中に〇日以上出勤した者を支給の対象とする」と記載されている場合、育休に入るタイミングや期間次第ではボーナスが一切支給されないこともあります。
減額支給されるパターンと同じく期間中の出勤日数に応じて算定する手法であり、その期間中に規定の出勤日数を満たすことができなければ支給対象から外れてしまいます。
特に、賞与算定期間が切り替わるタイミングと育休に入るタイミングが重なる人、育休期間が半年から1年以上ある人は注意しましょう。
全ての休職に対して一律の賞与算定方式を適用するのであれば、出勤日数に応じて一切支給しなくても違法ではありません。
育休だけを理由にボーナスを支給しない(減らす)のは違法

育休中にボーナスがもらえるかは会社により異なりますが、育休だけを理由にボーナスを支給しない(減らす)のは違法です。
例えば「育休を取ったから支給しない」「育児中の人は一律で不支給としている」という場合、「不利益な扱い」やマタハラ(イクハラ)に該当する可能性があります。
同じく、育休だけを理由にした復職後給与の減額・役職の降格・正社員からパートへの転換など雇用形態の変更も不利益扱いに該当するので注意しましょう。
ただし、育休取得以外を理由とした、一般的な範囲での決定であれば違法にはなりません。
全社員一律でボーナスが減らされている場合や、就業規則・給与支払規定に則った算定である場合は合法です。
育休中にボーナスをもらったら税金や保険料はどうなる?

育休・産休中のボーナスに関する税金・保険料の取扱いについても知っておきましょう。
社会保険料は免除になる
育休・産休中は社会保険料が免除されます。
事前に会社に申請しておけば、期間中に健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれることはありません。
免除期間は、休みに入った月から休みが終わる前月までです。
産休から続けて育休に入る場合には、新たに育休用の申請手続きが必要です。
所得税・雇用保険料は控除される
育休・産休中であっても、ボーナスや給与の支給があった場合には、休みに入る前と変わらず所得税の対象となります。
同様に、ボーナスや給与がある期間には雇用保険料も負担することとなります。
翌年支払う住民税の算定基礎には含まれる
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得をベースに決定され、翌年1年かけて月割で給与から控除されます。
つまり、賞与が高ければ高いほど、翌年支払う住民税も高くなるということです。
とはいえ、所得税や雇用保険料と違って収入が発生したタイミングで直ちに給与から控除されるものではないため、翌年に向けた蓄えをしておけば問題ありません。
なお、前年の収入分に対する住民税を今支払っている場合であっても、賞与から控除されることはありません。
賞与から控除されるのは所得税と雇用保険料のみであり、住民税はあくまでも毎月支給される給与だけから控除されることとなります。
育休中で給与がない場合、普通徴収にして自ら銀行やコンビニで市区町村宛てに支払うか、特別徴収のままにして育休から復帰した後に支払うか、どちらかになるのが一般的です。
ボーナスをもらっても育休給付金は減額されない
育休中にボーナスをもらっても、育休給付金が減額されることはありません。
よく「育休中に単発で復帰したり別の企業でアルバイトをしたりして賃金を受け取ると育児休業給付金がその分減額される」という話を聞きますが、賞与は育児休業給付金の算定基礎に含まれないので安心です。
厚生労働省において「賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲」という取り決めがされており、「臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」と明記されているので注目しておきましょう。(※)
賞与は「臨時の賃金」であるため、毎月定額で受け取る定期収入とは異なるという観点から、育児休業給付金の算定に影響しないのです。
育休中にボーナスがもらえない・減額される理由

ここでは、改めて育休中にボーナスがもらえない・減額される理由を解説します。
育休中とはいえ会社に在籍はしているため「ボーナスがもらえない(減額される)」と聞くとがっかりしてしまいますが、まずは理由を探っていくことが大切です。
就業規則・賃金規定で支給対象が明記されているから
就業規則・賃金規定で支給対象が明記されている場合、その対象にのみボーナスを支給する形で問題ないとされています。
ボーナスの支給に関する明確な法律はなく、会社の裁量に任されているのがポイント。
つまり、ボーナスを支給してもしなくても、支給対象を誰にしても、ある程度会社の自由とされているのです。
育休取得者だけを支給対象から外すなど基本的な法律に抵触する就業規則・賃金規定にすることはできませんが、まずは自分の会社の規定をチェックしてみましょう。
算定期間中の出勤日数が査定額に影響するから
算定期間中の出勤日数が査定額に影響する場合、育休中はほぼ確実に減額支給または不支給となります。
育休中は基本的に出勤できず、規定の出勤日数を満たすことができないのが現状です。
また、算定期間途中で育休に入った場合でも、休職した日数に応じて減額されてしまうので満額受け取るのは難しいかもしれません。
厚生労働省のガイドラインにも「賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取扱いに該当しません」と明記されています。
原則として、ボーナスは期間中に働いてくれた人に対する労いの賃金と考えておくとよいでしょう。
(※)厚生労働省「就業規則における育児・介護休業等の取扱い」
会社の業績が悪化していて一律減額・支給停止となっているから
会社の業績が悪化していて、一律減額・支給停止となっている場合もあります。
この場合、育休取得者だけでなく1日の欠勤もなくフルで出勤した人も減額・支給停止となっていることが多いのがポイント。
残念ながらボーナスは毎回100%の支給が約束されているものではなく、ほとんどの会社が業績に応じての支給としています。
育休中は会社の状態がわかりづらく、ボーナス支給・不支給に関する連絡も滞りがちになってしまうため、疑問に思ったら一度会社へ問い合わせてみるとよいでしょう。
育休中でもなるべく多くのボーナスをもらう方法

育休中は出勤できないため賞与が減額・不支給になるのは致し方無いとわかっていても、家計のことを考えるとなるべく多くのボーナスが欲しいのが本音です。
ここでは、子育て中でもなるべく多くのボーナスをもらう方法について解説します。
ボーナス算定期間が切り替わるタイミングで産休・育休に入る
ボーナス算定期間が切り替わるタイミングで産休・育休に入ることにより、ひとつ前の算定期間中はフルで出勤できていた扱いとなります。
大きな欠勤さえなければ欠勤控除もされないので、ほぼ満額に近い金額を受け取ることができるでしょう。
ただし、次の算定期間中は全日休職の扱いとなるため、次のボーナスはゼロになる覚悟が必要です。
それでも中途半端に欠勤控除されるより受け取れる金額が大きそうなときは、産休・育休に入るタイミングを検討しておきましょう。
早めに保育園を見つけて復職する
ボーナスをもらうには「出勤していること」が大前提となるため、早めに保育園を見つけて復職するのもひとつの手段です。
保育園は早くて生後57日目以降から利用できるため、それ以降に空きさえあればいつ入園させてもよいのがメリット。
子どもと過ごす時間を大切にして満期まで育休を取ることも、十分な収入を得るために早めに復職してボーナスを満額もらうことも可能です。
無理なく続けるためにもまずは時短正社員として復職するなど、生活リズムも大切にしながら決めましょう。
育休以降の収入が不安なときの対処法

育休以降の収入が不安なときは、思い切って転職を検討するのがおすすめです。
目先の給与やボーナスに問題がなくても、将来的な可能性が低いと年齢とともに収入を上げていくのは難しくなるでしょう。
ボーナスについて揉めたり給与が据え置きのまま伸びなかったりすると、仕事へのモチベーションにも影響します。
ここでは、育休以降の収入が不安なときの対処法を解説します。
業績が安定している会社に転職する
安定した収入を期待するのであれば、まずは業績が安定している会社に転職するのが先決です。
業績が安定している会社では激しく収入が上下することがなく、ボーナスも毎年安定して支給されます。
将来性も高いので、働きぶりや実績に応じて少しずつ給与も上がっていくでしょう。
転職エージェントを活用すれば、業界内外からの評判が良く安定している会社や、事業拡大中で人を積極採用している会社もわかります。
インターネット上のリサーチだけでは掴みにくい情報も得られるので、本格的に転職するべきか迷っているときでも相談してよいでしょう。
時短勤務でも稼ぎやすい会社に転職する
育休明けは時短勤務するワーママが多いですが、時短勤務でも稼ぎやすい会社に転職する方法もあります。
例えば、そもそもベースとなる給与が高い会社に転職できれば、時短勤務にして多少手取りが減っても十分な額を稼げるかもしれません。
同様に、時短勤務でも実力主義で客観的な人事評価をしてくれる会社であれば、働きぶりややる気に応じてワーママでもどんどん昇給・昇格が目指せます。
他にも、住宅手当・資格手当など各種手当が充実している会社に転職し、時短勤務でも年収を上げることは可能です。
子どもが大きくなり、フルタイムに戻せばさらに稼ぎやすくなるので、金銭的な不安を払拭できます。
キャリアアップできる可能性が高い会社に転職する
キャリアアップできる可能性が高い会社であれば、マミートラックに突入することなく働けます。
目先の給与に問題がなくても、将来的に給与が上がる可能性がないのであれば、妥協するかどこかで転職を検討するかしかありません。
実力に応じてしっかり人事評価してくれる会社であれば、実績や役割に応じた納得感のある給与になるよう調整してくれます。
頑張りが評価として返ってくるからこそ、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。キャリアアップ思考の人におすすめしやすい転職先と言えます。
キャリアと育児の両立は「リアルミーキャリア」にご相談ください

「リアルミ-キャリア」は、ワーママ転職や時短正社員転職に特化した転職エージェントです。
ワーママはキャリアと育児の両立に悩むことが多く、給与・ボーナスに関する悩みも決して珍しくありません。
「育児中にボーナスがもらえないことがわかり、2人目以降の出産時にこの会社にいてよいか迷い始めた」
「育休から復帰した後の給与が思うように伸びず、長期的な収支計画を立てづらくなった」
などの悩みは、転職で解決できるかもしれません。
金銭面での条件が良いだけでなく、働き方や評価制度も充実している会社に転職できれば、理想的なワーママライフとなるでしょう。
今後の収入について不安がある方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
育休中の社員に満額のボーナスを出す会社もあれば、減額支給・不支給とする会社もあります。
産休・育休に入るタイミングに応じて変動することもあるので、まずは自社の就業規則・賃金規定をチェックしてみましょう。
不明点があれば、育休中はもちろん、育休に入る前でも早めに質問して解消しておくのがおすすめです。
また、業績の悪化や今後の成長可能性の低さが原因でボーナス不支給(減額)となっている場合、早めに転職した方がよいかもしれません。
リアルミーキャリアでは、業界内外から評判が高く、人材も積極採用中の成長企業から寄せられる求人を多数扱っています。
ワーママ向け転職エージェントだからこそできるサポートも多いので、転職による年収アップを期待したい方はお気軽にご相談ください。
ワーママ特化型の転職エージェント
「リアルミーキャリア」の特徴

【リアルミーキャリアの特徴】
①育児との両立が整いやすい求人紹介
┗時短・リモート・フレックスなど
②手軽に転職活動できる
┗やり取りはすべてLINEでOK
③キャリアアドバイザーはワーママ多数
┗共感力&提案力バツグン
④入社までのサポートをおまかせ!
┗書類作成代行・面接対策などもOK
リアルミーキャリアは、ワーママに特化した転職エージェントです。
取り扱っている求人は、制限なしの時短勤務やリモート、フレックスなど、柔軟に仕事ができる環境がそろっています。
※会員登録ページへ移動します
ママ友に教えたい率95%!
リアルミーキャリアで転職した方の声
転職活動を終了された方へアンケートを取った結果、「リアルミーキャリアを他の人に勧めたい」と回答した方は95%※でした。
サービスをご利用いただいた方の声を一部ご紹介します。

リモートワークができるようになり、前より子供との時間が持てるようになりました。中抜けで通院できることも転職して良かったなと感じています。
これまでずっと立ち仕事だったので、デスクワークでの肩凝りは初体験です。でも小さなことですが、自由にトイレにいけたり、飲みたい時にコーヒーが飲めることも仕事によってこんなに違うんだなぁと感じています。
(30代 インサイドセールスへ転職)

毎日バタバタで大変ですけど、勤務時間が「私の時間」になり、とっても充実していて、イキイキしています。
同期、先輩方、上司共に皆さん本当に良い方で、何よりママが多い事が心強いです!!!
改めて素敵な企業を紹介して下さった事に感謝申し上げます。
社内にリアルミーから入社した人が多く、みんな口をそろえて「リアルミーめっちゃ良い」と言っています。
(30代 経理へ転職)
※アンケート実施時期:2020~2024年、有効回答数:762
時短正社員で転職するなら、「リアルミーキャリア」。
キャリアアドバイザーは8割がワーママなので、あなたの状況やご希望に寄り添った転職支援が叶います。
※会員登録ページへ移動します

